展覧会情報Exhibition Information
次回の展覧会Next Exhibition
予告
2026/2/21(土)〜2026/4/5(日)
10:00〜17:00
開館20周年特別展 生誕1200年 歌仙 在原業平と伊勢物語
平安時代前期に活躍した在原業平(825~880)は、天皇の孫で和歌に優れた貴公子です。その「歌仙」として、また「恋多き歌人」としての人物像は、彼の和歌にくわえ、『伊勢物語』の主人公に仮託されることで拡散していきました。2025年は、業平の生誕1200年にあたります。 これにちなみ、現在でも人気が高い業平と『伊勢物語』を題材に生み出された絵画・工芸等の作品を集め、そのイメージの広がりの豊かさと、造形の魅力を探ります。
2025年度は、三井記念美術館が2005年10月に開館してから20周年にあたります。この特別展は、これを記念して開催する特別展の第二弾です。
2025年は
展覧会の趣旨
平安時代前期に活躍した在原業平(825〜880)は、天皇の孫で和歌に優れた貴公子として知られます。その「歌仙」として、また「恋多き歌人」としての人物像は、彼の和歌にくわえ、『伊勢物語』の主人公に仮託されることで拡散していきました。
2025年は、業平の生誕1200年にあたります。これにちなみ、現在でも人気が高い業平と『伊勢物語』を題材に生み出された絵画・工芸・茶道具等の作品を集め、そのイメージの広がりの豊かさと、造形の魅力を探ります。加えて、和歌の典拠の一つとされる『古今和歌集』や、近世における普及の一端を担った版本・絵入本などの典籍を通じて、『伊勢物語』の成立と普及の過程についても展示いたします。
展示構成
展示構成は以下のように展示室ごとのテーマで展示いたします。
- 展示室1
- ダイジェスト伊勢物語
- 展示室2
- 伊賀耳付花入 銘業平
- 展示室3
- 如庵 「能の業平」
- 展示室4
- 絵画化された伊勢物語
- 展示室5
- 歌仙在原業平と伊勢物語
1,歌仙在原業平 2,伊勢物語の成立 3,伊勢物語の展開 - 展示室6
- 伊勢物語の名所
- 展示室7
- 伊勢物語の意匠化と芸能化
1,留守模様とデザイン化 2,伊勢物語の芸能化
主な展示作品
展示室1ダイジェスト伊勢物語
伊勢物語は全125段の章からなっています。この中から一般的にもよく知られた章段を15選び、各章段ごとに絵巻・色紙・かるた・
最初は、歌仙業平の姿を岩佐又兵衛が描いた重要文化財 三十六歌仙図額の業平像(図1)をご覧いただきます。

重要文化財
三十六歌仙図額 在原業平 像 1面
岩佐又兵衛筆 江戸時代・寛永17年(1640)
仙波東照宮蔵(埼玉県立歴史と民俗の博物館寄託)図1
続いて重要文化財の伊勢物語絵巻から、
伊勢物語
貝合わせの
瀬戸落穂手茶入(銘

重要文化財
伊勢物語絵巻 第4段「西 の対 」部分 1巻
鎌倉時代・13~14世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図2
展示期間:2/21〜3/15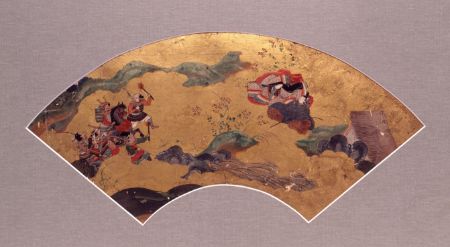
伊勢物語
芥川 ・武蔵野図扇面 1面
江戸時代・17世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図3

伊勢物語
合貝 第23段「筒井筒 」 1組
江戸時代・18世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図4
中興名物 瀬戸落穂手茶入 銘田面 1口
江戸時代・17世紀 三井記念美術館蔵図5
展示室2伊賀耳付花入 銘業平
全体に変形(デフォルメ)が強く、無造作な耳が付き、自然釉が織りなす景色は、古伊賀花入の特徴で、千利休の弟子七哲の一人にあげられる古田織部(1544~1615)の好みが反映されているとされます。利休的な規格を破った「破格の美」といわれ、利休亡きあとの茶の湯界をリードしました。
この花入は、『大正名器鑑』編纂の折に、関東にあった伊賀花入の名作5点が集められ「

伊賀耳付花入 銘業平 1口
桃山時代・16~17世紀 三井記念美術館蔵図6
展示室3如庵 「能の業平」
如庵写しの茶室ケースでは、床に
展示室4絵画化された伊勢物語
中世の作品では、香雪美術館所蔵の「伊勢物語図色紙」(図7)に要注目です。こちらは全17点のうち、2025年11月の根津美術館における特別展「伊勢物語 美術が映す王朝の恋とうた」に未出品の8点を展示いたします。いずれも所蔵館以外では初公開の作品となります。また、後述する『
近世の作品では、しみじみとした抒情をたたえる、
このほか、いわゆる「
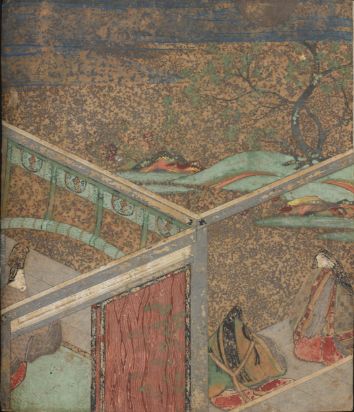
伊勢物語図色紙 第69段「君や来こし」 1枚
南北朝〜室町時代・14〜15世紀 香雪美術館蔵図7
展示期間:3/17〜4/5
八橋・龍田川図屏風 6曲1双
江戸時代・17世紀 和泉市久保惣記念美術館蔵図8
重要文化財
蔦 の細道図屏風深江芦舟 筆 6曲1隻
江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵
(Image:TNM Image Archives)図9
展示期間:2/21〜3/7
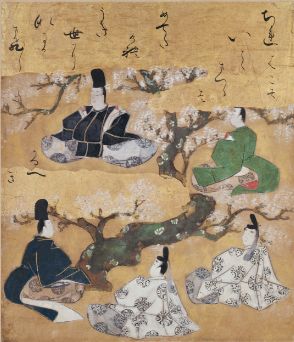
伊勢物語図色紙 第82段1「渚の院の桜」 伝俵屋宗達筆 1幅
江戸時代・17世紀 個人蔵図10
業平東下り図
鈴木其一 筆 1幅
江戸時代・19世紀
遠山記念館蔵図11
展示期間:3/17〜4/5
見立業平涅槃図
英一蝶 筆 1幅
江戸時代・18世紀
東京国立博物館蔵
(Image:TNM Image Archives)
図12
展示期間:2/21〜3/15
展示室5歌仙在原業平と伊勢物語
1,歌仙在原業平
10世紀初頭に成立した最初の勅撰和歌集『
在原業平(825~880)は、
古今集の時代から約300年後の13世紀初頭に八番目の
2,伊勢物語の成立
現在我々が手にする125章段の『伊勢物語』は、藤原定家による天福2年(1234)書写の天福本がもとになっていますが、伊勢物語の成立については様々な研究があり、本展の図録では関西大学名誉教授山本登朗氏による「歴史のなかの伊勢物語」をご寄稿いただいております。
『伊勢物語』は、業平の和歌による歌物語ですが、業平が生きた時代に最も近い『古今和歌集』には、伊勢物語の中でも重要な章段で登場する話が多くあり、詞書の長いものがあるのも悩ましいところです。細部で違いもあり、双方の影響関係が問題とされています。ここでは当館で所蔵する『古今和歌集』(図14)、『後撰和歌集』、『拾遺抄』(図15)などの古い和歌集で業平に関する部分を展示いたします。
3,伊勢物語の展開
近世以降、伊勢物語の受容層を増加させるきっかけとなったのが、いわゆる「
『嵯峨本伊勢物語』登場以降も、伊勢物語を扱った絵入りの版本はたびたび刊行されました。その中から本展では、
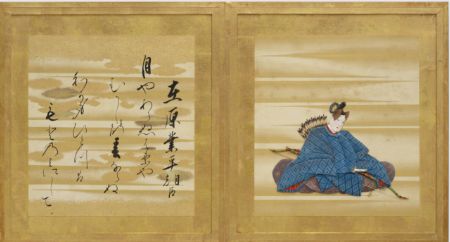
押絵六歌仙帖 吉田元陳 下絵 1帖
江戸時代・18~19世紀 三井記念美術館蔵図13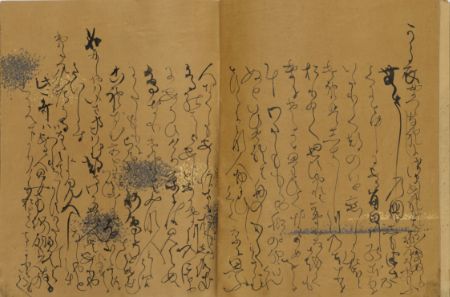
古今和歌集 上・下 2冊
烏丸光広 筆
江戸時代・17世紀 三井記念美術館蔵図14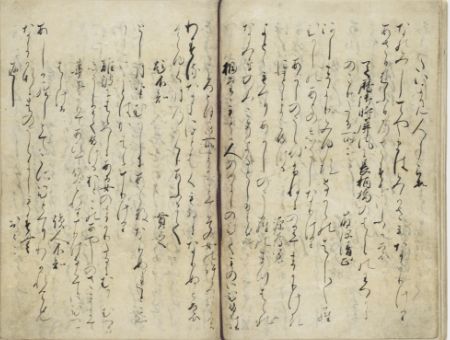
重要文化財
拾遺抄 1冊
鎌倉時代・13世紀 三井記念美術館蔵図15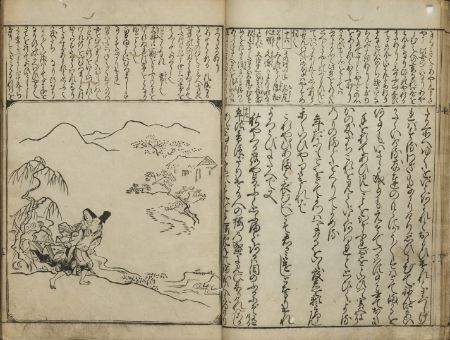
新版伊勢物語頭書抄 菱川師宣画 3冊
江戸時代・延宝7年(1679) 和泉市久保惣記念美術館蔵図16
展示室6伊勢物語の名所
伊勢物語にゆかりのある名所や、伊勢物語にちなんだ名所が日本の各所にあります。
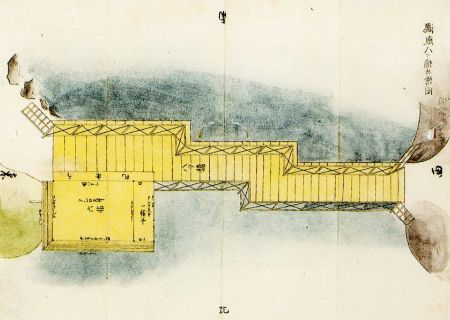
重要文化財
瀧殿 八ツ橋共絵図(大工頭 中井家 関係資料のうち) 1枚
江戸時代・18世紀
中井正知氏・中井正純氏蔵 (大阪市立住まいのミュージアム寄託)
[撮影:京極寛]図17
展示室7伊勢物語の意匠化と芸能化
1,留守模様とデザイン化
漆工品や染織品などの工芸品のなかには、伊勢物語の章段のなかから選んだテーマを意匠化(デザイン化)したものが多くありますが、留守模様のデザインが多いと言えます。
蔦の細道蒔絵文台硯箱(図18)は、全体に蒔絵で雲形に蔦の葉が散らされ、修行者が背負う
色絵竜田川図向付(図19)は、尾形乾山の作で紅葉と流水を大胆にデザインした色絵陶磁器です。伊勢物語からの発想とすれば、第106段「龍田川」の留守模様です。
同じ龍田川がデザインされたと思われる打掛(龍田川に鳥)(図20)は、鳥がいるところから伊勢物語の留守模様とはいい難いのですが、「龍田川」と称しているところは、伊勢物語のイメージも含まれているといえます。
江戸時代における着物のデザイン集ともいえる

蔦 の細道蒔絵文台硯箱 1具
江戸時代・17世紀 遠山記念館蔵図18
色絵竜田川図向付 5客 尾形乾山作
江戸時代・18世紀 大和文華館蔵図19
打掛 (龍田川に鳥) 1領
江戸〜明治時代・19世紀 文化学園服飾博物館蔵図20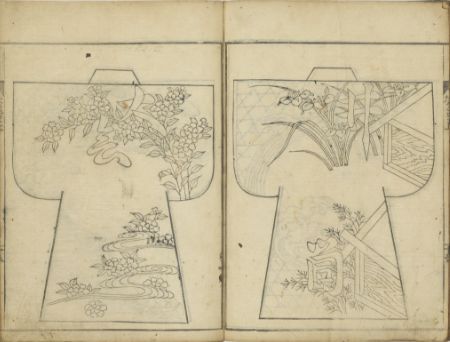
雛形本 「高砂雛形 」(井筒) 1冊
江戸時代・元禄3年(1690) 三井記念美術館蔵図21
2,伊勢物語の芸能化
伊勢物語は芸能の世界でも採り上げられています。ここでは能の世界での関係作品を展示いたします。
当館には旧金剛宗家伝来の能面が54面伝わっていますが、何れも重要文化財に指定されています。その中から展示室7では

重要文化財
能面中将 (鼻まがり) 伝福来 作 1面
室町時代 三井記念美術館蔵図22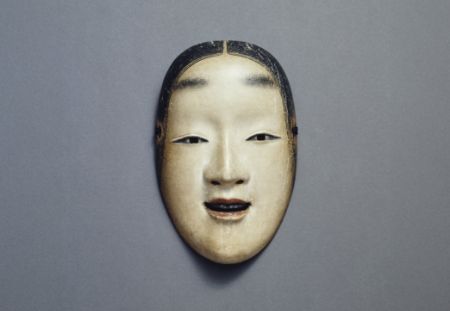
重要文化財
能面孫次郎 (ヲモカゲ) 伝孫次郎作 1面
室町時代 三井記念美術館蔵図23
- 会期
- 2026年2月21日(土)~4月5日(日) ※会期中、展示替えを行います。
- 開館時間
- 10:00〜17:00(入館は16:30まで)
- 休館日
- 2月22日(日)、3月16日(月)
- 主催
- 三井記念美術館
- 監修
- 河田昌之(大阪芸術大学教授、和泉市久保惣記念美術館館長)
- 協力
- 和泉市久保惣記念美術館、伊勢物語絵研究会
- 入館料
- 一般 1,500(1,200)円
大学・高校生 1,000(800)円
中学生以下 無料- ※70歳以上の方は1,200円(要証明)。
- ※20名様以上の団体の方は( )内割引料金となります。
- ※リピーター割引:会期中、半券のご提示で、2回目以降は( )内割引料金となります。
- ※障害者手帳をご呈示いただいた方、およびその介護者1名は無料です(ミライロIDも可)。
- 音声ガイド
- 音声ガイドでわかりやすく解説いたします。(日本語のみ、貸出料700円)
- 入館
- 予約なしでご入館いただけます。
展示室内の混雑を避けるため入場制限を行う場合があります。
- お問い合わせ先
- 050-5541-8600(ハローダイヤル)
